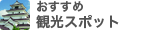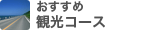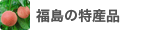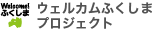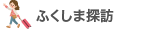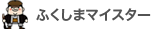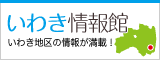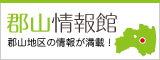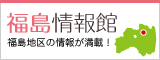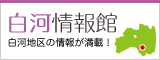会津エリアの特産品

- 会津漆器(あいづしっき)
- 天正18年(1590年)、蒲生氏郷(がもううじさと)が領主になり、近江の木地師(きじし)や塗り師(ぬりし)を会津に移住させてから本格的に造られました。江戸時代には蒔絵(まきえ)、金箔(きんぱく)などの技術改良をし、有数の漆器の産地となりました。加飾(蒔絵)体験もできます。

- 会津絵ろうそく
- 絵ろうそくは武家社会で珍重された高級品で、菊や牡丹・梅などの華やかな絵柄が描かれ、主に神仏用や結婚式などに飾られました。会津のお土産品としても喜ばれたようです。今でも一本一本が手作りです。会津若松市内には絵付け体験ができるところもあります。

- 会津木綿(あいづもめん)
- 領主 加藤嘉明(かとうよしあき)が寛永4年(1627年)に会津に移った時、伊予松山(いよまつやま)から織師(おりし)を招いて伝習したのが起源といわれ、色鮮やかな縞模様(しまもよう)が特徴です。体験教室もあります。

- 会津桐製品(あいづきりせいひん)
- 桐下駄やタンスなど、木目が美しい会津桐は高い評価を受けています。琴の材料としても日本一の素材です。体験教室もあります。

- 陶磁器(とうじき)
- 素朴な味わいのある、会津の伝統的な焼き物です。いくつかの窯元(かまもと)では「手びねり」や「絵付け」等の体験もできます。

- 初音(はつね)
- 初音は、子供たちが元旦の朝買ってもらい正月の三ヶ日神棚に飾り、後でお下げしてからオモチャにして遊ぶ小さな竹笛です。笛の胴の部分を親指と人差し指でふさぐと「ホー」とやや低い音が、人差し指を離すと「ケキョ」にあたる高い音が出ます。今はあまり見られなくなりましたがひと昔前の子供たちはよくこの初音を吹いて遊んでいました。

- 起き上がり小法師(おきあがりこぼし)
- 転んでもすぐに立ち上がるところから、粘り強さと健康のシンボルとして縁起(えんぎ)が良いとされています。家族や財産が増えるよう人数より1個多く買う習わしになっており、十日市(会津若松市の初市)には欠かせない縁起物です。約400年前、当時の藩主 蒲生公が無役の藩士に作らせて、正月に売り出したのが始まりとされています。 体験教室もあります。

- 風車(かざぐるま)
- 羽を豆で止めることから「まめ(=元気)で、くるくる働けるように」との願いが込められた正月の縁起物です。体験教室もあります。

- 赤べこ(あかべこ)
- 起源は平安時代にまでさかのぼるといわれている会津の伝統的な張り子玩具で、昔から厄除けの縁起物として親しまれています。ゆらゆらと首をふる姿はとてもユーモラスです。ベコは会津弁で牛のこと。体験教室もあります。

- 会津唐人凧(あいづとうじんだこ)
- 「べろくんだし」ともいわれ、戊辰戦争の時に籠城(ろうじょう)中の鶴ヶ城(つるがじょう)から士気を鼓舞(こぶ)するためにあげられたといわれています。体験教室もあります。

- 会津天神(あいづてんじん)
- 学問の神様である天神様にあやかり、子供のすこやかな成長を願う伝統玩具のひとつ。以前は頭が練りもので胴は張子で作られていましたが、現在は全て張子でできています。京風で上品な顔立ちをしています。
↑ページトップへ












 日本語
日本語 English
English