ふくしまマイスター 第1回「とんぼ玉マイスター」

マイスター特集 第1回
「とんぼ玉マイスター」 田辺 晴美(たなべはるみ)さん

最初にとんぼ玉製作をしたのは7年前。彫金や鍛金の材料費の一部の為に友人とアクセサリー製作として始めました。バーナーなどの機材は一通りそろっていたので軽い気持ちで始めたんです。しかし思っていたより奥が深く、徐々にのめり込んでいきました。
とんぼ玉製作を始めてしばらくすると、デザインなどで自己流の限界を感じるようになり、色々な有名作家さんの展示会を見て歩くようになりました。ある時、城下鮎子(しろしたあゆこ)さんの作品を見たら一目惚れしてしまい、作品を購入するだけじゃなく、半分押しかけで弟子入りしちゃいました(笑)。 ※城下さんの代表作にはジブリ公式の「トトロのとんぼ玉」(三鷹の森ジブリ美術館にて販売)などがあります。

弟子入り後も最初は失敗する事もしばしば。ガラスの添加物の化学反応でせっかく作った作品が変色しちゃったり、余計な気泡が入って模様が曲がったり。やってはいけない素材の組み合わせなど、思ってた以上に覚えることが多くて苦労しました。離型剤の種類もたくさんあって、作家さんによっては離型剤も自作する方がいるんですよ。
雑貨店オーナーとしてとんぼ玉製作教室をするようになった今では、県外からも定期的に習いに来てくださる方もいらっしゃいます。製作教室は1回2時間ぐらいかかるんですが、その半分の1時間ぐらいは冷却時間なんです。待っている間にお茶を飲みながらお話ししたり、お店の商品を見たり、夕飯のお買い物に行く方もいましたね。いろんな人が習いに来てくださるのですが、その中には自分で機材をそろえて自宅でとんぼ玉製作を出来ようにしてしまうほど熱心な方もいるんです。これにはびっくりしました(笑)。機材を一通りそろえると結構な額になるんですが、そこまでしてもやりたいほどとんぼ玉製作を好きになってもらえたのはとてもうれしいですね。
「とんぼ玉」ができるまで。
01材料1

材料は彩色されたガラス棒がメインになります。さらにそれらを加工したガラス棒も部品として使用します。
02材料2

今回、部品は透明なガラスに白いガラスを螺旋状に巻いた「レース」や、金太郎アメの原理で断面が星柄になったものを使います。
03準備

星柄のガラスは、そのまま使用せずチップ状にします。
04機具

コンプレッサーとガスバーナー
05基礎部作成1

最初にベースとなるガラス棒を加熱します。この時、炎に直接かざし過ぎるとガラス棒が気温との温度差で破裂し飛び散る危険があるので、炎をくぐらせるようにして徐々に加熱します。
06基礎部作成2

ある程度ガラス棒に熱が通ったら先端から溶かしていきます。溶けたガラスが球状になるようにガラス棒を回しながら加熱します。
07基礎部作成3

必要な量が球状になったら芯棒の離型剤を加熱します。この加熱をしないと完成時、離型剤に残った水分などでガラスに気泡が出来てしまいます。
08基礎部作成4

離型剤を十分加熱したらガラスを巻きつけていきます。この時、手前側から奥に向かって回しながらガラス棒は芯棒と直角に、芯棒は水平になるように注意します。回転方向は破裂や跳ねた場合の危険防止のためです。
09基礎部作成5

巻きつけたらヘラとコテで大まかに成形します。
10装飾

装飾となるガラス(レース・星型のチップ・月を形成する黄色いガラス)を付けていきます。一種類の装飾を付けては成形を繰り返します。
11冷却

すべての装飾が完了したら冷却させます。こちらでは香炉灰に入れて約1時間、自然冷却させています。冬季は自然冷却でも急激に冷めてしまい、温度差で亀裂が入ってしまいます。そのため電気窯を使用して徐々に冷まします。
12洗浄

十分に冷却できたら芯棒から取り外し、とんぼ玉内部に残った離型剤もブラシ等で洗浄します。
完成

今回はストラップパーツを取り付けて完成です。
冷却時間も含め1時間半から2時間ほどで出来上がります。

「その他の部品・成形方法」
部品には今回使用したレースや星以外に花などもあります。
また、球状以外に成形することも可能です
■店舗データ
| 店 名 | 十月の南 |
|---|---|
| 住 所 | 郡山市久留米6-144 |
| 営業時間 | 10:30~17:00 |
| 定休日 | 日曜日、祝祭日 |
| TEL | 024-947-5195 |
| FAX | 024-947-5195 |
| URL | http://koriyama.welcome-fukushima.com/co/juugatsunominami/ |
【次回のマイスターは】
『渡辺だるま』渡辺 半次郎(わたなべはんじろう)さんです。

 日本語
日本語 English
English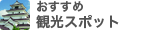
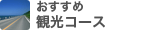
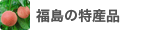

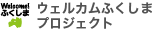
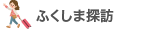
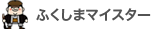

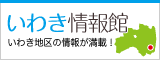
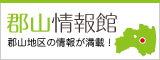
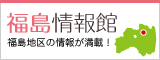

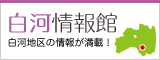



【取材後記】
取材者:松 倉
取材をする前は「ガラスを熱して加工すれば完成するもの」と簡単に思っていましたが、実際に製作するところを取材させていただくと予想をはるかに超える作業量でした。常に完成形を意識して溶けたガラスを成形し続けなければいけないので、とても集中力を必要とします。
田辺さんはにこやかに話しながら作業を見せてくださいましたが、「さすがマイスター」といった雰囲気でした。作品を冷却している間にも色々とお話を聞かせていただきました。子供のように目を輝かせてとんぼ玉や作家さんについて熱弁する姿が印象的です。
これからも
「お客さんに欲しいと思ってもらえるオリジナティーのある作品」
「作っていてドキドキする、自分も欲しいと思う作品」
そんなとんぼ玉を作りたいと話す田辺さん。
奈良時代にはすでに作られていたとんぼ玉ですが、科学の進歩に伴い様々な技法や薬品、機材が使われており、まだまだ進化を続けているようです。
奥深さの反面、基本的な注意事項を守ればどなたにも気軽に出来るそうで、体験教室では初心者にもわかりやすく教えてもらえます。ぜひ一度ご体験ください。